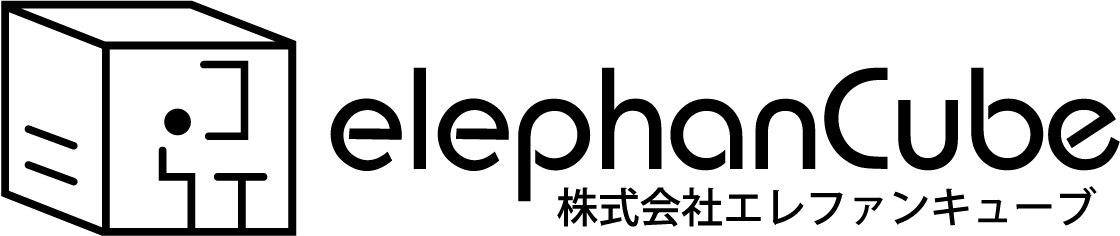平均寿命が伸び、「人生100年時代」と言われるようになった現代、一人ひとりの生き方や働き方にも大きな変化が訪れています。現代のビジネス環境は急速に変化しており、単なる専門知識や技術力だけでなく、柔軟な対応力やチームワーク、主体的に行動する力が求められています。
この記事では、社会人基礎力とは何か、社会人基礎力が注目される背景や、人生100年時代の社会人基礎力3つの視点などについて紹介します。
<目次>
社会人基礎力とは
社会人基礎力とは、2006年に経済産業省によって提唱された「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことです。そして、2018年に「人生100年時代」ならではの視点を念頭に、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力として、「人生100年時代の社会人基礎力」と新たに定義されました。
経済産業省:「社会人基礎力」
社会人基礎力の重要性
社会人基礎力は、すべてのビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルです。以前は、主に新入社員や若手社員にとって必要な能力とされてきた社会人基礎力ですが、現在は年齢や立場、役職などに関わらず、すべてのビジネスパーソンにとって欠かせない能力となっています。
ビジネス環境の変化
グローバル化やデジタル技術の進化に伴い、企業が求める人材像も変化しています。デジタルスキルの重要性が増す一方で、単なる技術力や専門知識だけでなく、柔軟な対応力や主体的に行動する力、コミュニケーション能力や協調性といった社会人基礎力がますます重要になっています。
人生100年時代におけるキャリア形成
技術の進歩により、人間の寿命は延び、「人生100年時代」といわれています。この長いキャリアを通じて活躍し続けるために、社会人基礎力の重要性が増しています。経済産業省は、社会人基礎力の3つの能力と12の能力要素を基盤としつつ、自己認識やリフレクション(振り返り)を通じて、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切り開く上で必要と位置づけています。
人材の定着と組織の成長
多くの企業では、人材の定着率向上や即戦力化を課題としています。社会人基礎力を高めることで、職場への適応力が向上し、離職率の低下や生産性の向上につながります。
また、社会人基礎力を備えた人材が増えることで、組織全体のパフォーマンス向上やイノベーションの促進が期待できます。企業の競争力を高めるためにも、社会人基礎力の向上は欠かせません。
社会人基礎力:3つの能力12の能力要素
社会人基礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力と、12の能力要素から構成されています。自らの仕事と学びを振り返りながらキャリアを築いていくことは、働く上で欠かせない能力となっています。
前に踏み出す力(アクション)
一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力。指示を待つだけではなく、自ら考え、行動できるようになることが求められます。例えば、未経験のことを成長のチャンスと捉えて挑戦する、一人で解決できない課題の場合は他人に協力を依頼する、目標時間を設定して作業するなどを指します。
【能力要素】
- 主体性:物事に進んで取り組む力
- 実行力:目的を設定し確実に行動する力
- 働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力

考え抜く力(シンキング)
疑問を持ち、考え抜く力。論理的に答えを出すだけでなく、自ら課題提起して解決のために深く考えられるようになることが求められます。例えば、上手くいかなかった場合に原因を考える、複数の考えの中から最善の方法を考える、よりよい解決方法のために批判的な思考で物事を見ることができるなどを指します。
【能力要素】
- 課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力
- 計画力:課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
- 創造力:新しい価値を生み出す力

チームで働く力(チームワーク)
多様な人々とともに、目標に向けて協力する力。グループ内の協調性にとどまらず、多様な人々との繋がりや協働を生み出す力が求められます。例えば、相手の立場に配慮して発言をする、対立した意見でも直ぐに反論しない、臨機応変に対応する、相手との関係性を理解して適切な言動をする、挨拶や5分前行動を心がける、自分にとってストレスとなる状況を理解するなどを指します。
【能力要素】
- 発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力
- 傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力
- 柔軟力:意見の違いや立場の違いを理解する力
- 情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
- 規律性:社会のルールや人との約束を守る力
- ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力

人生100年時代の社会人基礎力:3つの視点
少子高齢化やグローバル化などを背景に、一つのスキルだけで活躍し続けることは困難となり、働くことと学ぶことの一体化が必要不可欠になりました。また、社会人としての基礎力とマインドを持ち続け、専門スキルや新しいスキルを常にアップデートし続けていくことが求められています。
このような状況を踏まえ、2018年に再定義された「人生100年時代の社会人基礎力」では、これまでの3つの能力と12の能力要素に、さらに3つの視点が追加されました。「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され、能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置付けられています。
経済産業省:「社会人基礎力」
どう活躍するか(目的)
自己実現や社会貢献に向けて行動することで、行動を促すための力として「前に踏み出す力」が重要になります。多様な働き方に適応する力も求められます。
何を学ぶか(学び)
能力を発揮するためには自分の強みと弱みを把握し「考え抜く力」が重要になります。自己成長を続けるために何が必要か、何を学ぶかを考え、スキルをアップデートしていく必要性が高まっています。
どのように学ぶか(統合)
自分の能力や経験と他の多様な人々の得意なことを組み合わせて、目標達成を目指します。個人として新しいことに挑戦したり、企業としてキャリア支援を行うなどして、全体のスキルや経験・体験総量をあげます。統合して新しい価値を創造するため「考え抜く力」や「チームで働く力」が重要になります。
社会人基礎力向上のための取り組み
社会人基礎力は、個人・企業・社会がそれぞれの立場から取り組みを進め、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の能力を掛け合わせながら、3つの視点を循環させていくことで成り立ちます。
個人では、キャリアや強み・弱みを振り返り自己分析を行います。その上で、どの能力を伸ばすのか、あるいは補完が必要なのかを検討します。自分以外の人からの意見を聞くことも有効です。また、書籍やeラーニングを用いたスキルアップや人的ネットワークの構築が考えられます。学びで得た知識を、実践において積極的に活用することも重要です。
企業では、キャリア支援のための研修の実施や公正な人事評価システムの整備、柔軟な働き方への対応などがあります。自社の魅力を可視化することで、社員のモチベーション向上を図ることも大切です。また、自社だけではなく、社外での活躍の場を提供することも効果的です。
まとめ
社会人基礎力は、すべてのビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルです。以前は、主に新入社員や若手社員にとって必要な能力とされてきた社会人基礎力ですが、現在は年齢や立場、役職などに関わらず、すべてのビジネスパーソンにとって欠かせない能力となり、「長く活躍し続ける力」へと進化しています。学びを継続し、学びを仕事に活かすこと、そして常に問い続ける姿勢が、これからもさらに必要となるでしょう。
eラーニング教材:社会人基礎力シリーズ
社会人基礎力は、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、12の能力要素で構成されており、これらの能力は特定の職種に限らず、あらゆる職場で求められるスキルであり、社会人として円滑に業務を遂行するための基盤となります。この12の能力要素を学びます。
最終更新日: 2025-03-22